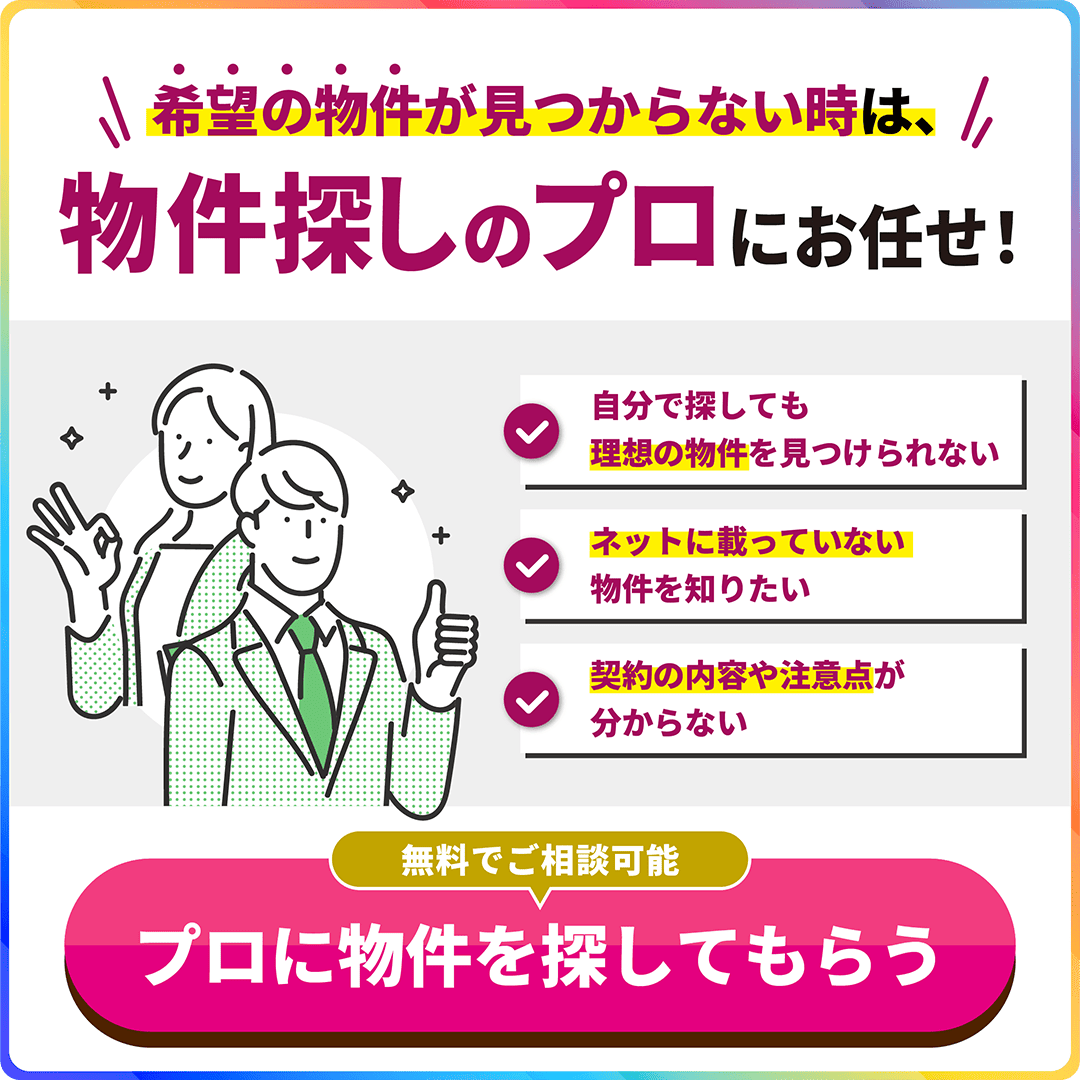公開日:2025/09/29
「いつかふたりで、温かい家庭を築きたいね。」
そう語り合い、将来の住まいについて考え始めたLGBTカップルの皆さん、こんにちは。
理想のマイホームは、人生における大きな夢のひとつ。しかし、住宅ローンとなると、様々な不安や疑問が湧いてくるかもしれません。特に、LGBTカップルにとっては、住宅ローン審査における課題がいくつか存在することも事実です。 「そもそも、住宅ローンを組むことができるのだろうか?」 「パートナーとの関係をどう説明すればいいのだろう?」 かつては、このような不安を抱える方も少なくありませんでした。しかし、近年、社会の多様性に対する理解が深まるにつれて、金融機関の対応も少しずつ変化してきています。 このコラムでは、LGBTカップルが住宅ローン審査をクリアし、夢のマイホームを手に入れるためのノウハウを徹底解説します。住宅ローン審査の基礎知識から、審査に通りやすくするための対策、実際に住宅ローンを組めたカップルの成功事例まで、具体的な情報をお届けします。
さあ、一緒に一歩踏み出しましょう。愛のカタチを、温かい住まいに変えるために。

LGBTQ+カップルが住宅ローンで直面しやすい課題
まず、LGBTQ+カップルが住宅ローンを検討する際に、どのような課題に直面しやすいか理解しておきましょう。
パートナーシップの法的位置づけ
現在の日本では同性婚が法的に認められていないため、パートナーは民法上の「親族」とはみなされません。これにより、夫婦を前提とした住宅ローン(ペアローン、連帯債務、収入合算など)の利用が困難になるケースがあります。
金融機関の理解度
金融機関によっては、LGBTQ+カップルの関係性に対する理解が不十分で、古い慣習に基づいて審査を進めようとすることがあります。
団体信用生命保険(団信)の問題
住宅ローンとセットになることが多い団体信用生命保険は、「夫婦」が加入することを前提としている場合があり、万一の際にパートナーに保障が及ばない可能性があります。
情報不足
LGBTQ+カップル向けの住宅ローンに関する情報が少なく、どこに相談すれば良いか分からない、という声もよく聞かれます。
攻略法1:事前準備を徹底する!
不安を解消し、スムーズな住宅ローン借入れを実現するためには、事前の準備が非常に重要です。
(1) 関係性を証明する書類を揃える
パートナーシップ宣誓制度の利用
全国の自治体で導入が進む「パートナーシップ宣誓制度」を利用し、宣誓書や受理証明書を取得しましょう。法的効力は限定的ですが、二人の関係性を公的に証明する重要な書類となり、金融機関への説明材料として役立ちます。
公正証書での合意書作成
公証役場で「合意契約書」や「任意後見契約」などの公正証書を作成することも有効です。財産分与、生活費の分担、医療同意など、将来を見据えた二人の関係性を明確にし、万が一の事態に備えられます。
(2) 個人の信用情報を確認する
それぞれがこれまでのクレジットカードやローンの返済状況に問題がないか、信用情報機関(CIC, JICC, KSCなど)に開示請求して確認しておきましょう。これは、ローン審査の基本中の基本です。
(3) 専門家への相談を検討する
LGBTQ+フレンドリーな不動産会社やファイナンシャルプランナー(FP)に相談することをおすすめします。彼らはLGBTQ+カップルの住宅購入をサポートした実績があり、適切なアドバイスや金融機関の紹介をしてくれる可能性があります。
攻略法2:住宅ローンの組み方を検討する
同性婚が認められていない現状で、LGBTQ+カップルが利用しやすい住宅ローンの選択肢を見ていきましょう。
(1) 単独名義でのローン
最も現実的な選択肢の一つです。どちらか一方の収入を基にローンを組み、その名義人が団信に加入します。
メリット:手続きが比較的シンプルで、団信の問題もクリアしやすい。
デメリット: 借入額が一人分の収入に限定されるため、希望の物件価格に届かない場合があります。また、購入物件の名義も原則として単独になります。
(2)一部の金融機関が提供する「ペアローン」「連帯債務」
近年、LGBTQ+カップルにも「ペアローン」や「連帯債務」の利用を認める金融機関が増えてきています。
「ペアローン」:二人がそれぞれ住宅ローンを組み、お互いが連帯保証人となる形式。二人の合算収入で借入額を増やせます。
「連帯債務」: 一人が主債務者となり、もう一人が連帯債務者となる形式。二人の収入を合算して審査を受けることができます。
ポイント:これらの形式は、団信の加入対象者や保障内容が金融機関によって異なります。必ず事前に詳細を確認しましょう。パートナーシップ宣誓書の提出を求められることがほとんどです。
(3) フラット35の活用
【フラット35】は、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供する、長期固定金利の住宅ローンです。
**「収入合算」**の要件が比較的柔軟で、**親族以外の「内縁関係」**でも認められる場合があります。この「内縁関係」の解釈に、パートナーシップ宣誓書が有効に働くことがあります。
メリット: 金融機関側の判断に左右されにくく、安定した金利で借り入れが可能。
デメリット: 団信は任意加入で、別途検討が必要です。
攻略法3:金融機関選びがカギ!
LGBTQ+フレンドリーな金融機関を見つけることが、住宅ローン攻略の最も重要なポイントです。
公式に「多様な家族の形を応援」と表明している金融機関を探す:大手銀行の中にも、LGBTQ+カップル向けに積極的に情報発信をしているところがあります。公式サイトやニュースリリースを確認しましょう。
地方自治体の取り組みをチェックする:パートナーシップ制度を導入している自治体の中には、提携金融機関がLGBTQ+カップル向け住宅ローン商品を提供しているケースもあります。
専門家からの紹介:LGBTQ+カップルの住宅購入に詳しい不動産会社やFPは、実際に融資実績のある金融機関を知っています。彼らのネットワークを活用しましょう。
攻略法4:団体信用生命保険(団信)と万が一への備え
団信は、ローン契約者が死亡・高度障害になった場合、残りのローン残高が保険金で完済される制度です。LGBTQ+カップルが団信を利用する際は、以下の点に注意が必要です。
単独名義の場合:主債務者が団信に加入すれば、万一の際にはローンが完済されます。残されたパートナーが住居を失うリスクは軽減されますが、物件の名義人ではないため、事前に所有権や居住権に関する公正証書を作成しておくことが賢明です。
ペアローン・連帯債務の場合:金融機関によって、二人とも団信に加入できるか、保障内容がどうなるか異なります。必ず契約内容を詳細に確認し、不明な点は質問しましょう。
団信以外の生命保険の活用:団信だけでは不安な場合や、加入できなかった場合は、民間の生命保険を検討しましょう。それぞれが受取人をパートナーに指定できるような保険に加入することで、万一の際の経済的なリスクをカバーできます。
攻略法5:公正証書で未来の安心を固める
住宅ローンを組む段階で、万が一の別離や、一方の死亡といった将来のリスクに備え、以下の合意事項を公正証書として残しておくことを強くお勧めします。
不動産の所有権の割合:共同名義にする場合、それぞれがどのくらいの割合で所有権を持つか。
ローンの返済負担割合:毎月の返済額をどのように分担するか。
万が一の別離時の対応:物件の売却、一方への引き継ぎ、清算方法など。
まとめ:諦めない心と賢い情報収集が未来を拓く
LGBTQ+カップルが住宅ローンを組む道のりは、従来の夫婦に比べてまだハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、制度の進化や金融機関の理解が進み、選択肢は確実に増えています。
大切なのは、「私たちには無理だ」と諦めずに、積極的に情報収集を行い、LGBTQ+カップルのサポート実績のある専門家を頼ることです。
愛するパートナーと理想の家で暮らす夢を、ぜひ実現させてください。一歩踏み出す勇気が、きっと未来の扉を開きます。
LAKIA不動産京橋店
大阪府大阪市都島区東野田町2-9-13
TEL 06-6354-3510
https://lakia-kyobashi.com/
スタッフコラム一覧
-
2025/10/26 同性カップルの同棲・半同棲するメリットとデメリットとは?
-

2025/09/29 LGBTカップルのための住宅ローン攻略法:愛のカタチを住まいに変える
-
2025/09/11 同性カップルがマンションを購入するには?
-

2025/07/04 同性ルームシェアの落とし穴と成功の秘訣
-
2025/06/23 トランスジェンダーの方にとって住みやすい大阪の街や環境とは?
-
2025/05/09 トランスジェンダー婚活の現状と注意点をご紹介
-
2025/04/13 【解決には課題が残る】LGBTカップルの不動産購入と相続問題
-
2025/04/11 LGBTフレンドリーな賃貸物件の探し方と安全&快適な住まい選びのポイント
-
2025/02/10 LGBTはなぜ入居拒否されるのはなぜ?入居の実態と回避する方法を解説!
-
2025/02/09 トランスジェンダーと性同一性障害の違いについて